しらべてサイエンス・ロケ下見
…98年8月16日 城ヶ島
 城ヶ島の西端、灘ヶ崎。垂直に近い南傾斜の三崎層。
城ヶ島の西端、灘ヶ崎。垂直に近い南傾斜の三崎層。
 火山噴出物の地層。特に炎状になった火山灰層が目立つ。
一種の液状化現象で、未固結の段階で上下の地層に密度差の逆転構造があるときにつくられたもの。
下位の密度の小さい水を含んだ火山灰層が浮き上がり、スコリア質の上位の層が垂れ下がってできた。
城ヶ島京急ホテルと相模亭の南側の岩場。
火山噴出物の地層。特に炎状になった火山灰層が目立つ。
一種の液状化現象で、未固結の段階で上下の地層に密度差の逆転構造があるときにつくられたもの。
下位の密度の小さい水を含んだ火山灰層が浮き上がり、スコリア質の上位の層が垂れ下がってできた。
城ヶ島京急ホテルと相模亭の南側の岩場。
 やや変位の大きい断層で、白い火山灰層がずれていることがよくわかる。
ここを撮影に使いましょう、という相談をした。
やや変位の大きい断層で、白い火山灰層がずれていることがよくわかる。
ここを撮影に使いましょう、という相談をした。
 岩場を東へ移動。右が担当のNED鈴木千加志さん。左はこの番組の構成作家、笹本妙子さん。
岩場を東へ移動。右が担当のNED鈴木千加志さん。左はこの番組の構成作家、笹本妙子さん。
 斜行葉理。流れの速い、堆積速度の大きい場で形成される構造。
すでにある地層の模様を切って、新しい地層が上にたまることを繰り返し、互い違いに地層が積み重なっている。
斜行葉理。流れの速い、堆積速度の大きい場で形成される構造。
すでにある地層の模様を切って、新しい地層が上にたまることを繰り返し、互い違いに地層が積み重なっている。
 馬の背洞門の遠景。大正時代まではこの穴のすぐ下まで海が来ていたが、
関東大震災の地震の際に、このあたりは1.5m隆起し、こんなに高い位置に来てしまった。
馬の背洞門の遠景。大正時代まではこの穴のすぐ下まで海が来ていたが、
関東大震災の地震の際に、このあたりは1.5m隆起し、こんなに高い位置に来てしまった。
 海岸段丘。緑に覆われた上半分は陸上堆積のローム(火山灰)。
冬から春であれば草が枯れて、4.9万年前の東京軽石層が白い帯となってロームの下側に見える。
およそ6万年前に離水した、三崎面。高度は28m程度。
海岸段丘。緑に覆われた上半分は陸上堆積のローム(火山灰)。
冬から春であれば草が枯れて、4.9万年前の東京軽石層が白い帯となってロームの下側に見える。
およそ6万年前に離水した、三崎面。高度は28m程度。
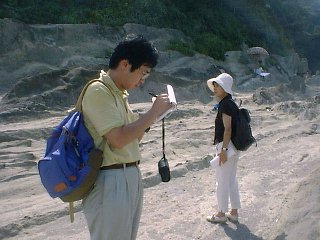 東端(安房崎)の岩場にて。地層の逆転構造と断層が見られる。
メモを取る鈴木さん。
東端(安房崎)の岩場にて。地層の逆転構造と断層が見られる。
メモを取る鈴木さん。
 安房崎北側。コンクリートの橋を境に、傾斜が異なるのがわかる。
ここに断層があり、斜めに地層が接合している。
安房崎北側。コンクリートの橋を境に、傾斜が異なるのがわかる。
ここに断層があり、斜めに地層が接合している。
戻る
indexに戻る
 城ヶ島の西端、灘ヶ崎。垂直に近い南傾斜の三崎層。
城ヶ島の西端、灘ヶ崎。垂直に近い南傾斜の三崎層。
 火山噴出物の地層。特に炎状になった火山灰層が目立つ。
一種の液状化現象で、未固結の段階で上下の地層に密度差の逆転構造があるときにつくられたもの。
下位の密度の小さい水を含んだ火山灰層が浮き上がり、スコリア質の上位の層が垂れ下がってできた。
城ヶ島京急ホテルと相模亭の南側の岩場。
火山噴出物の地層。特に炎状になった火山灰層が目立つ。
一種の液状化現象で、未固結の段階で上下の地層に密度差の逆転構造があるときにつくられたもの。
下位の密度の小さい水を含んだ火山灰層が浮き上がり、スコリア質の上位の層が垂れ下がってできた。
城ヶ島京急ホテルと相模亭の南側の岩場。
 やや変位の大きい断層で、白い火山灰層がずれていることがよくわかる。
ここを撮影に使いましょう、という相談をした。
やや変位の大きい断層で、白い火山灰層がずれていることがよくわかる。
ここを撮影に使いましょう、という相談をした。
 岩場を東へ移動。右が担当のNED鈴木千加志さん。左はこの番組の構成作家、笹本妙子さん。
岩場を東へ移動。右が担当のNED鈴木千加志さん。左はこの番組の構成作家、笹本妙子さん。
 斜行葉理。流れの速い、堆積速度の大きい場で形成される構造。
すでにある地層の模様を切って、新しい地層が上にたまることを繰り返し、互い違いに地層が積み重なっている。
斜行葉理。流れの速い、堆積速度の大きい場で形成される構造。
すでにある地層の模様を切って、新しい地層が上にたまることを繰り返し、互い違いに地層が積み重なっている。
 馬の背洞門の遠景。大正時代まではこの穴のすぐ下まで海が来ていたが、
関東大震災の地震の際に、このあたりは1.5m隆起し、こんなに高い位置に来てしまった。
馬の背洞門の遠景。大正時代まではこの穴のすぐ下まで海が来ていたが、
関東大震災の地震の際に、このあたりは1.5m隆起し、こんなに高い位置に来てしまった。
 海岸段丘。緑に覆われた上半分は陸上堆積のローム(火山灰)。
冬から春であれば草が枯れて、4.9万年前の東京軽石層が白い帯となってロームの下側に見える。
およそ6万年前に離水した、三崎面。高度は28m程度。
海岸段丘。緑に覆われた上半分は陸上堆積のローム(火山灰)。
冬から春であれば草が枯れて、4.9万年前の東京軽石層が白い帯となってロームの下側に見える。
およそ6万年前に離水した、三崎面。高度は28m程度。
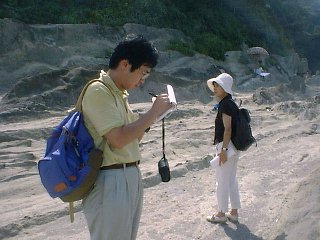 東端(安房崎)の岩場にて。地層の逆転構造と断層が見られる。
メモを取る鈴木さん。
東端(安房崎)の岩場にて。地層の逆転構造と断層が見られる。
メモを取る鈴木さん。
 安房崎北側。コンクリートの橋を境に、傾斜が異なるのがわかる。
ここに断層があり、斜めに地層が接合している。
安房崎北側。コンクリートの橋を境に、傾斜が異なるのがわかる。
ここに断層があり、斜めに地層が接合している。