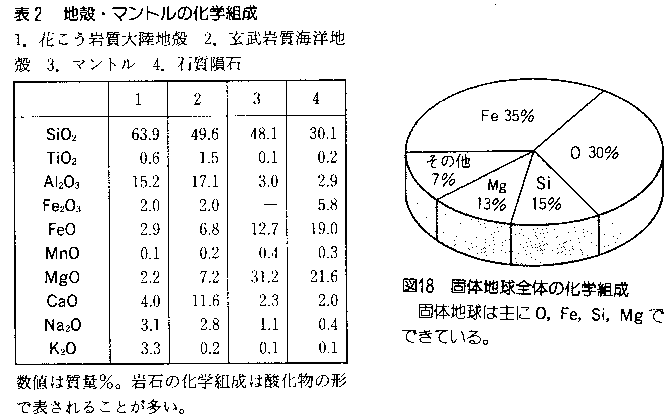
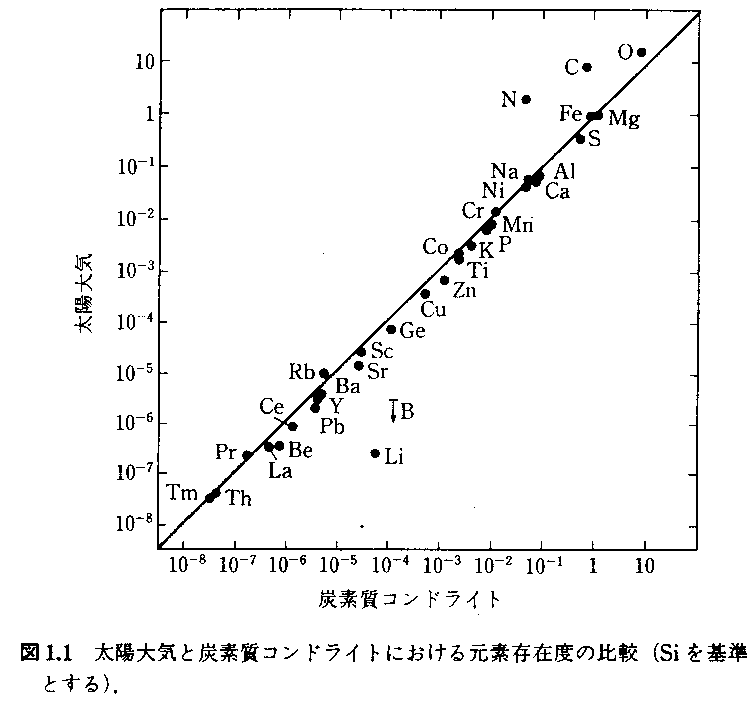
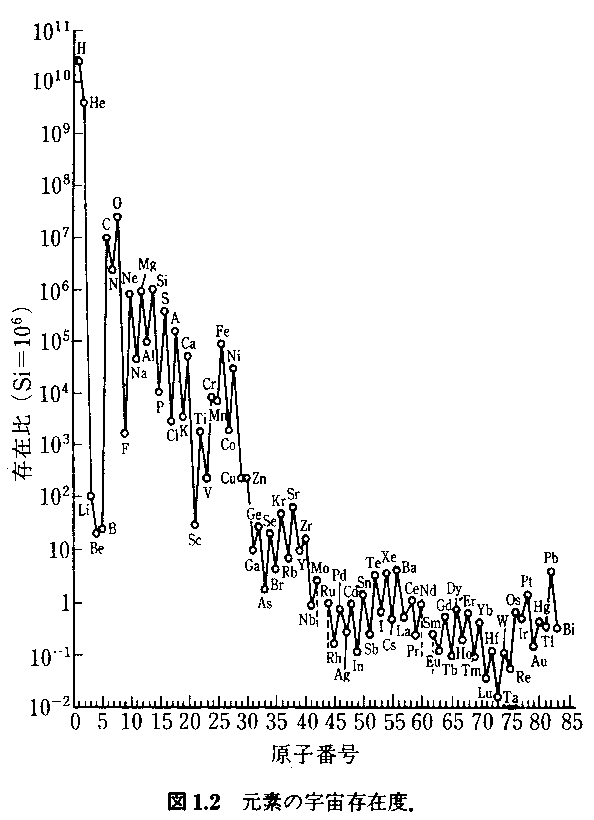
F1G 地学 1学期期末試験問題
7.10(木曜)2限実施 萩谷出題
*図の引用:啓林館・高等学校地学IB、「地球化学」講談社より。
以下の問いに答えよ。解答は解答用紙の所定の欄に記入すること。また、計算問題はすべて有効数字2桁で答えるものとする。
アイソスタシーについて、次の設問に答えよ。
1)右図の、水に木片を浮かべる実験で、アイ
ソスタシーを表す式はh1、h2、ρ1、ρ2を用い
てどのように書けるか。ただし、空気や大気圧
の存在は無視して良い。
2)h1とh2の比、すなわち水面上の高さと水面
下の深さの比は、木片の種類が同じであれば一定
の値を持つ。 h1/h2をρ1、ρ2を用いた式で表せ。
3)地殻の密度を2.7g/cm3、マントルの密度を
3g/cm3とする。厚さ30kmの地殻と厚さ60km
の地殻が隣り合っているとするとき、アイソスタ
シーから、後者は前者に比べてどのくらいの高度
差を持っていると考えられるか。計算せよ。ただ
し、計算の上で、地殻やマントルの密度はそれぞ
れ一定とし、空気や海水の影響などは考えない。
4)摂氏0度の水の密度は1.0g/cm3、同じ温度の氷の密度は0.92g/cm3である。2)の結果を参考にすると、水に浮かべた氷の水面上の高さはごく小さいはずであるが、南極海等で実際に見られる氷山は、h1/h2の値が0.1程度と、やや大きい場合がある。これはどうしてか。考えられる理由を述べよ。
地球の層構造について、以下の問いに答えよ。
1)地球に、主に金属鉄からなる核が存在することは、どのような証拠から導かれるか。実際に我々が調べることのできる、2つ以上の方法を説明せよ。
2)地殻とマントルの物質的な違い(物理性質の違いでもよい)について簡単に説明せよ。(解答例:電気抵抗の値が違う。マントルよりも地殻物質の方が小さい。)
次の文章を読んで、あとの設問に答えよ。
太陽系の元素存在度(元素の割合)は、いくつかの方法で詳しく計算されており、それは宇宙の平均的な元素存在度を表していると考えられることから、宇宙存在度とも呼ばれる。ある種の隕石(炭素質コンドライト)は、太陽系の元素存在度を非常によく反映していると考えられている。
太陽大気の元素存在度は、太陽大気を通過してきた太陽光のスペクトルを観測することで求められる。スペクトルとは、光の波長による強度分布のことで、プリズムで太陽光を分けたときの虹模様として我々にみえるものでもある。太陽光のスペクトルをよく調べると、虹模様の中に暗線という、暗い線が現れる。これは元素をつくる原子が、それぞれ元素によって決まった特定の波長の光を吸収するために起こる現象である。したがって、この吸収線を調べることにより、どの元素がどのくらい太陽大気に入っているかを知ることができる。
この方法は元素の存在度を知る方法として、太陽以外の天体にも応用できる。元素によって吸収する光の波長は、宇宙のどこでも同じであるからである。例えば、オリオン座の大星雲からの光を分光観測することにより、そこでは太陽系よりも重い元素(水素以外の元素)の割合が多くなっていることがわかっている。また、天体の放つ光のスペクトルを調べたときに、その吸収線の波長が本来の値からずれている場合も知られており、これはその天体と観測者であるわれわれとの間の相対運動による、ドップラー効果を見ているものと考えられる。
設問
1)問題文末尾の図(3,4ページ)を参考に、太陽大気の元素存在度と隕石のそれとがおおきく異なる元素の種類(ひとつまたはそれ以上)と、その理由を答えよ。解答は元素名でも元素記号でも良い。
2)太陽大気のデータに対して、隕石の化学組成を用いることのメリットを説明せよ。
3)オリオン大星雲などで、水素より重い元素の割合が多い(原子番号で鉄(Fe)までの元素が多い)ということは、どのようなことが原因として考えられるか。簡単に説明せよ。
4)地球上に鉄よりも重い(原子番号の大きい)元素が豊富にあることは、地球や太陽系の材料について何を意味するのか。簡潔に説明せよ。
岩石の分類と化学組成について、以下の文章の空欄を語句欄から適するものを選んで埋め、設問に答えよ。
地球型惑星である、( 1 )、( 2 )、( 3 )、( 4 )、及び小惑星、月は、太陽系の共通の材料からつくられ、全体としての化学組成もほぼ共通であると考えられている。これらの惑星のマントルは、主に( 5 )という岩石からできていると考えられる。( 5 )とは、そのほとんどをかんらん石(Mg2SiO4)という鉱物が占めていて、それに輝石(MgSiO3)という鉱物と、若干の他の鉱物からなる岩石である。
マントルの( 5 )が部分融解してマグマをつくり、マグマの( 6 )が周囲の( 5 )の( 6 )よりも小さいために、浮上して、地表または地表近くの低温の場で固結し、地殻の火成岩ができる。地球以外の惑星では、このマグマのほとんどは( 7 )質の化学組成を持ち、マグマが冷えてできる地殻の岩石としては、( 7 )か( 8 )ができる。この2つの岩石の組織は、前者は斑状組織であり、後者は等粒状組織が特徴である。構成する鉱物としては両者ともに有色鉱物としてかんらん石と輝石が、また無色鉱物としては( 9 )がみられる。
地球は例外的にSiO2成分の多いマグマも大量に生産され、かこう岩を特徴とする大陸地殻をつくっている。地球の大陸地殻は( 6 )が小さく、マントルの上に常に浮いている状態のため、分裂・大陸移動や集合・合体成長を繰り返し、新しいマグマを付け加えて、地球史の長い間に複雑な構造を持つようになっている。
堆積岩は、地表において大気や水、生命活動のために、風化-浸食-運搬-堆積といった過程を経て、岩石が変化したものである。堆積岩の特徴としては、層理や堆積構造を示すものが多く、また溶解や沈殿、生物の遺骸の濃集などによって、火成岩に比べて特殊な化学組成になったものがある。例として、石灰岩は、ほぼ純粋な炭酸カルシウム(CaCO3)、チャートは珪酸(SiO2)からなる。また、海水が蒸発したところでは、岩塩(NaCl)等も見られる。
変成岩のうち、( 10 )は、主に大陸の衝突の際に、地表近くにあった岩石が急速に地下深くに持ち込まれ、その場所の温度・圧力条件におうじた鉱物の集合に変化したものであり、片理や片状組織といった特徴を持つ。( 10 )は、衝突して厚くなった地殻の部分が、アイソスタシーによって隆起し、急速に侵食されることによって広く露出すると考えられる。アパラチアなどの古い造山帯に広く変成岩が露出し、一方アルプスやヒマラヤのような、できて間もない若い造山帯では、変成岩の露出が限られていて、それはこのような考えで説明できる。
語句欄:
太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、彗星、流紋岩、安山岩、玄武岩、閃緑岩、はんれい岩、かんらん岩、石英、カリ長石、斜長石、黒雲母、
密度、硬度、温度、圧力、価格、広域変成岩、接触変成岩、活断層、
設問:
現在、Mars Path Finder(MPF)による、火星表面の無人探査が進行中である。その探査の重要な目的に、火星にかつて生命が存在した痕跡を探したり、あるいは生命が誕生しうる環境が存在したことを、岩石の化学組成を分析することで示そうということがある。
では、火星の岩石の化学組成に、どのような特徴が検出できれば、上記のような火星生命の存在に関わる情報が得られることになるのか。上の文章を参考に、自分の考えを述べよ。
今学期の地学の授業で扱った項目のうち、2つを自分で選んで説明せよ。自分で調べた内容でも良い。
なお、参考までに、配布したプリントには、水の話2つ、プレート・テクトニクスの背景、元素存在度、おいしい水と河川の汚染の話、太陽スペクトルなどがある。
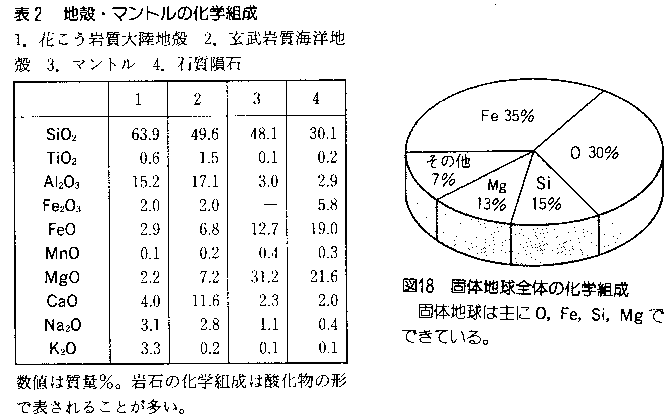
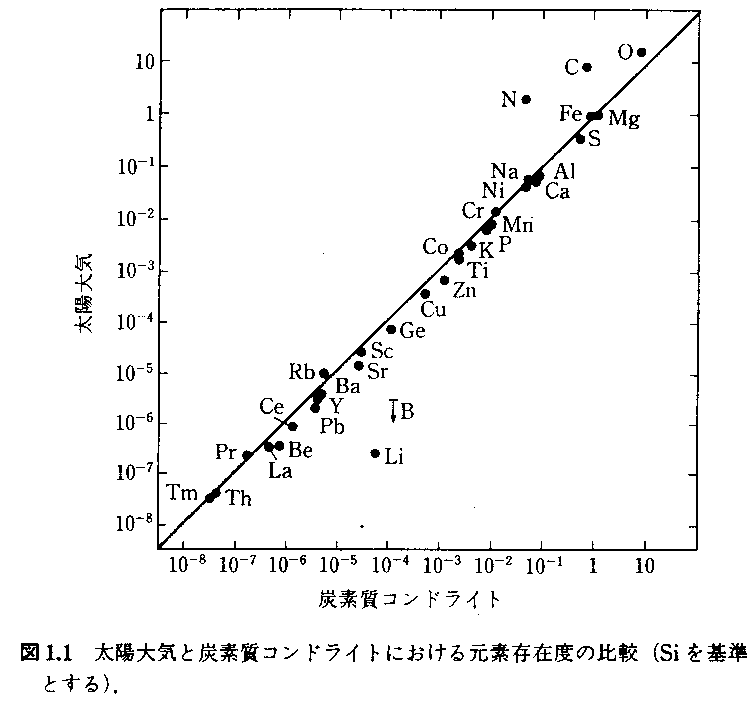
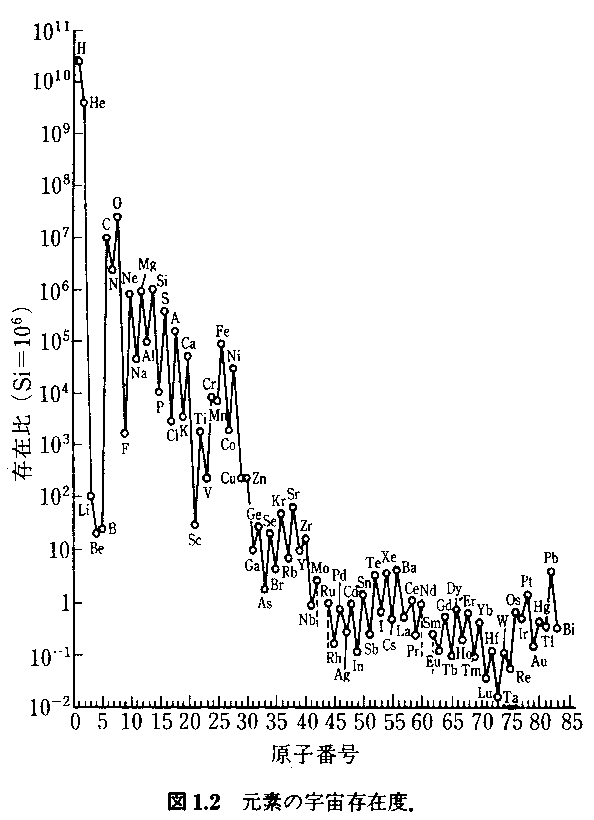
解答用紙
F1G 地学 1学期期末試験 1997.7.10 1限
Ⅰ1)
2)
3)
4)理由:
Ⅱ
1)方法1:
方法2:
2)地殻とマントルの違い:
Ⅲ
1)元素: 理由:
2)
3)
4)
Ⅳ
1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8) 9) 10)
設問:
Ⅴ
1)
2)
F1G 番号 氏名 得点